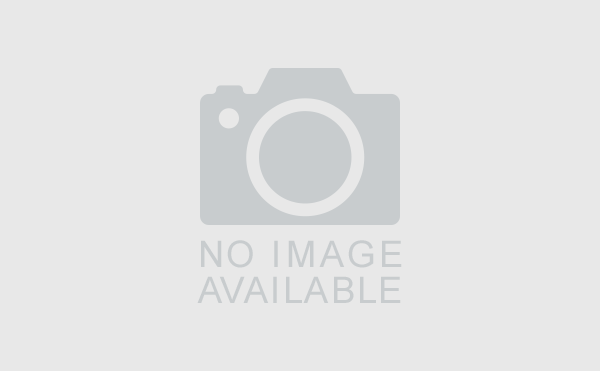夏バテに負けない東洋医学の養生と漢方薬のおすすめ
はじめまして。漢方外来を担当している吉住奈緒子と申します。
今年は6月頃から真夏のような暑さが続いています。日本の夏特有の暑さと湿度で体調を崩しがちな方も多いのではないでしょうか。今回は、夏バテに負けず夏を快適に過ごすためにおすすめの養生方法と漢方薬についてお話させていただきます。
夏に起こる「だるい」「食欲がない」「頭が重い」「寝つきが悪い」など、いわゆる「夏バテ」といわれる状態は、暑さや湿度、冷房による体の冷えなどが複雑に影響し、体内の「気(エネルギー)」や「水」のバランスが崩れることで起こると考えられています。
東洋医学では季節に応じた「養生」が重視されます。東洋医学で夏は「心(しん)」の季節ですが、心は血と関係し、精神活動や睡眠に深く関与します。また、汗をかきすぎることで「気」と「水」が同時に失われやすく、結果的にだるさや脱力感、のぼせ、不眠といった症状につながります。
【夏バテ予防の養生ポイント】
1. 水分補給は「質」と「タイミング」を意識しましょう
汗をかいた分を補うために水分補給は欠かせませんが、冷たい飲み物をがぶ飲みすると、胃を冷やして消化機能を傷めてしまい、食欲不振や腹部膨満を招くことがあります。水分補給には常温の麦茶、はとむぎ茶、白湯などがおすすめです。これらをこまめに少量ずつ摂取するのが理想です。もしも暑さに負けて冷たい飲み物や食べ物を取ってしまった時には、最後に温かいお茶や白湯を飲んで胃を温めましょう。
2. 食事は「脾(消化機能)」をいたわる内容に
冷やし中華やアイスクリームなど、夏に食べたくなる涼を求める食べ物は、どうしても胃を冷やして消化機能を弱らせてしまいます。夏こそ温かい汁物やおかゆ、雑炊など、消化にやさしい食事を意識しましょう。利水・清熱効果のある冬瓜、きゅうり、とうもろこし、緑豆、苦瓜なども夏におすすめの食材です。
3. 冷房と汗のコントロール
屋外との温度差が激しい環境では、体温調節機能が乱れ、自律神経にも負担がかかります。汗をかいた後は早めに拭き取り、冷房の温度設定を高めにしたり冷房の風が直接当たらないようにしたりして体が冷えすぎないように心がけましょう。また、冷房で冷え切ってしまった体を温めるには、お風呂に入るのもおすすめです。血行を良くして自律神経を整えるためにも、夏でも最低週に2回はゆっくり湯船につかりましょう。
【夏バテにおすすめの漢方薬】
◆ 清暑益気湯(せいしょえっきとう)
対象:だるさ、食欲不振、全身倦怠感、微熱、汗をかきやすい体質
解説:暑邪による体力低下を補う夏バテ用の処方です。補気薬が気を補い、潤いを保つ薬、熱を冷ます薬がバランスよく配合されており、エネルギー不足で体がだるく、ほてるタイプに適しています。
◆ 六君子湯(りっくんしとう)
対象:胃もたれ、食欲不振、軟便、 全身倦怠感
解説:夏の冷飲食で弱りがちな脾胃を立て直す代表的処方。消化機能を高め、胃もたれや吐き気を改善します。食後に疲れやすい方、冷え体質の方にも向いています。
◆ 五苓散(ごれいさん)
対象:むくみ、頭重感、口渇、尿量減少、二日酔い体質
解説:湿気による体内の水分滞留を改善する処方。利水作用のある生薬が含まれ、余分な水を尿として排出します。頭痛やめまい、下痢傾向のある方にも有効で、湿度の高い日本の夏に適しています。
これらの漢方薬は、市販薬としても入手可能ですが、体質や症状に合わないと効果が出にくいこともあります。使用にあたっては漢方専門の医師に相談することをおすすめします。
【おわりに】
東洋医学のアプローチでは、「未病=病気になる前の状態」に目を向け、早めの対処でバランスを整えることを重視します。夏バテはまさに未病の代表格。食事、水分、睡眠、冷え対策、そして必要に応じた漢方薬で、今年の夏も心と体を健やかに過ごしましょう。